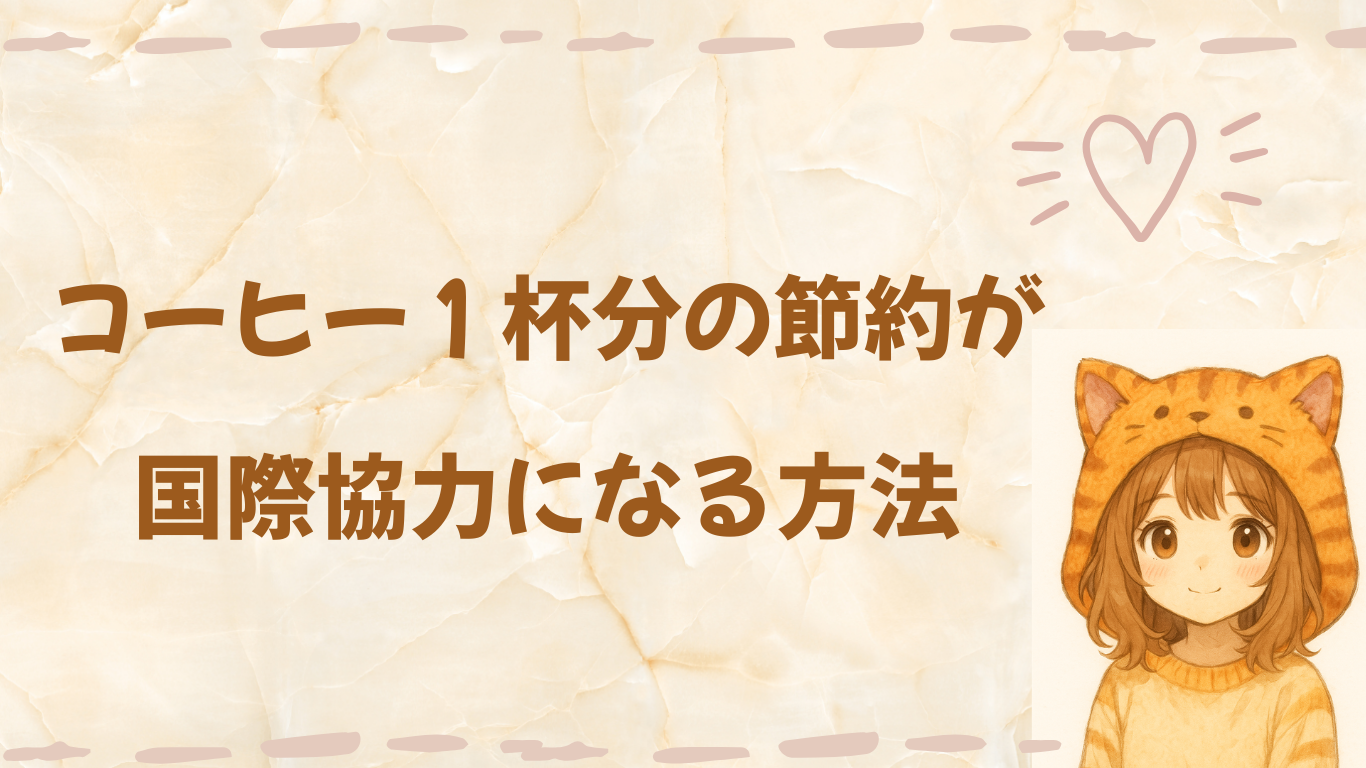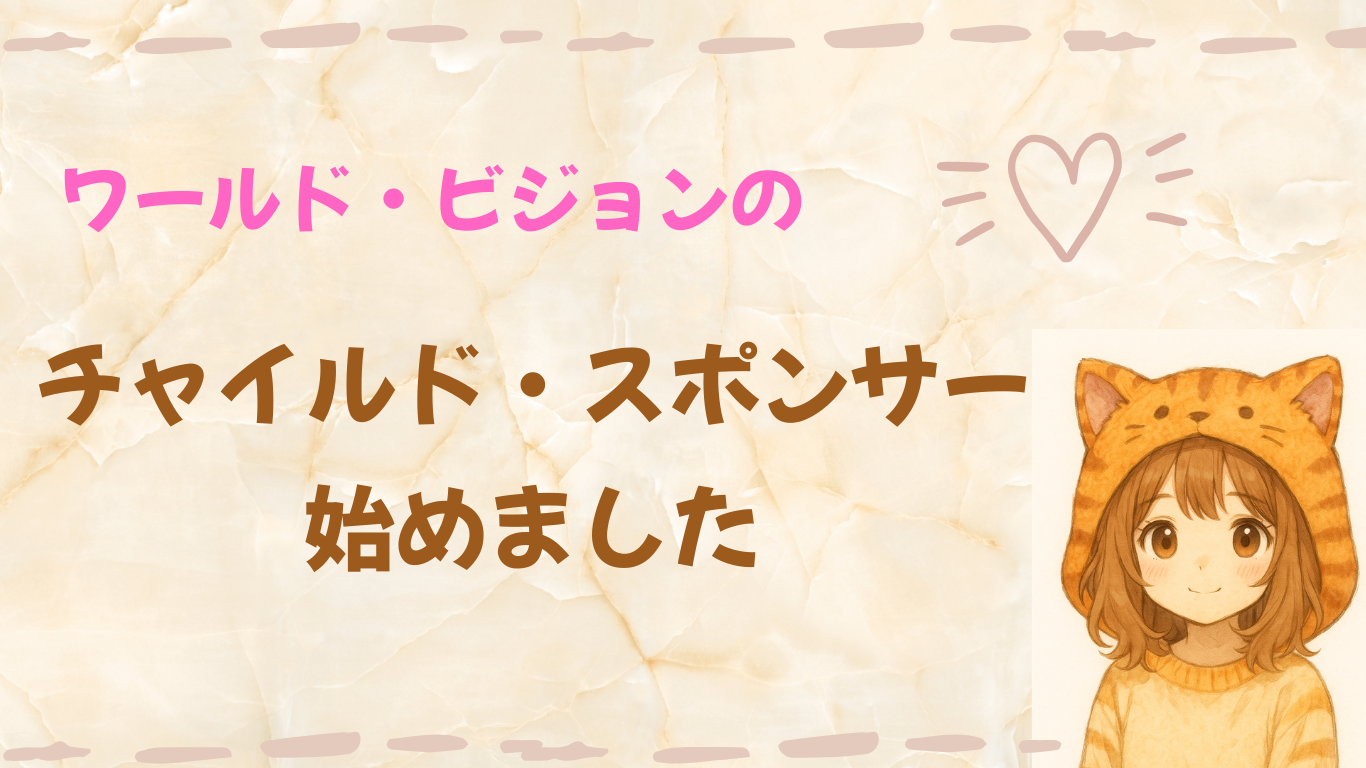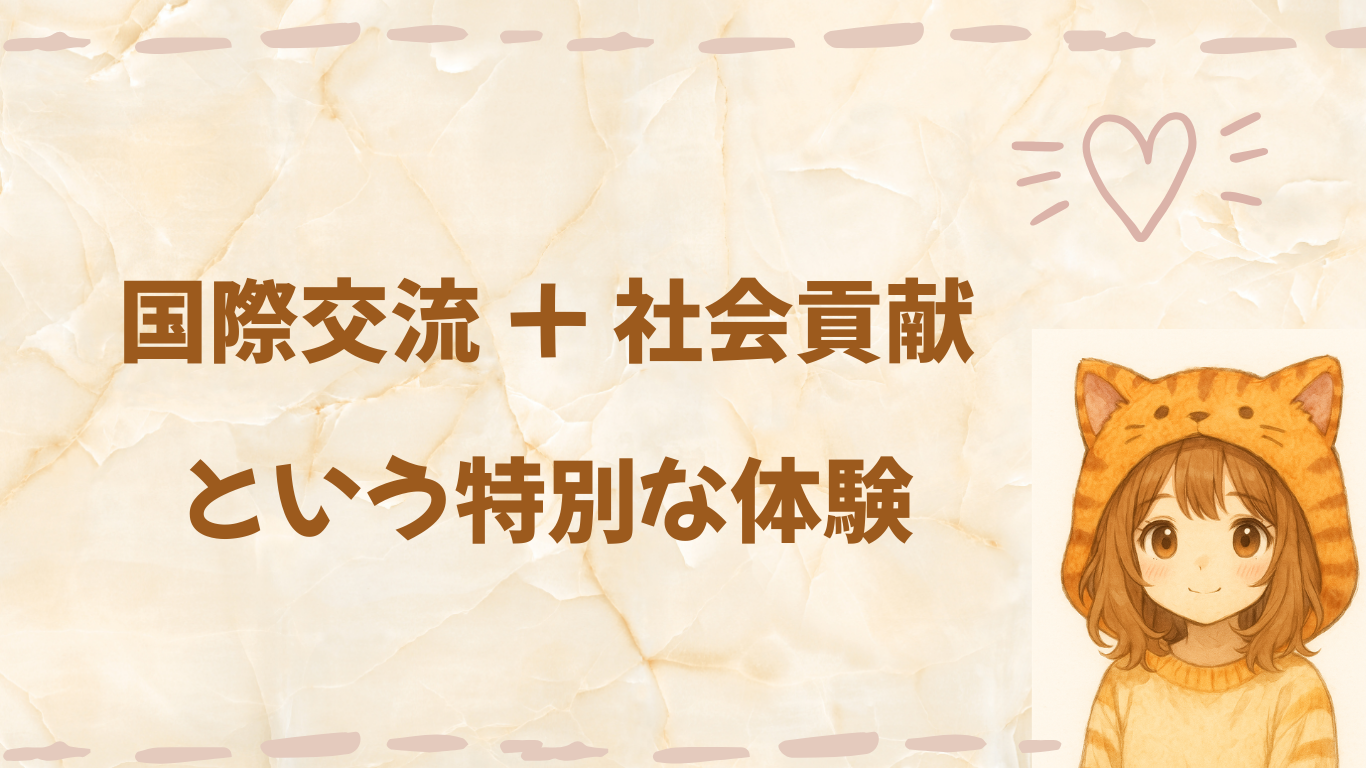世界陸上で見つけた「難民選手団」という存在


今、世界陸上が熱いですね!私は高校・大学生の時に長距離をやっていたので、毎晩TVに釘付けになっています。
こんにちは!最近は毎晩、世界陸上に夢中になっている、ぽかぽかです。
その世界陸上を観ていると、出場選手の国名が表示される画面に「難民選手団」という文字がありました。
えっ、難民選手団?
国じゃなくてチームなの?
そこから気になって難民選手団について調べてみると、深い背景と感動的なエピソードがたくさんあったので紹介します。
難民選手団って何?
難民選手団(ART/ワールドアスレティックス難民選手団)は、紛争や迫害によって故郷を追われたアスリートたちが国際大会に出場できるように設けられた特別なチームです。
国際オリンピック委員会(IOC)が2016年のリオ五輪からスタートさせ、現在は世界陸上やオリンピックでその姿を見ることができます。
彼らには所属がなく、国旗や国歌もありません。
ですが、オリンピック旗を背負って世界の舞台に立ち、「スポーツは国境を越える」ということを体現しています。
- 今回の世界陸上では6人の選手がARTとして出場。
- 男女比は「女子2人、男子4人」
- アシックスは世界陸連難民選手団をオフィシャルスポンサーとしてサポートしている

なぜこんな仕組みがあるのかな?難民選手団の意義はなんだろう?
- 故郷を追われた人が「競技を続けられない」「代表になれない」などスポーツの面で機会を失うことが多い。そういう人たちに「機会」を与えるという点で、この制度はとても重要。
- スポーツを通じて「難民であること」によるマイナスイメージを変える、「希望」「リジリエンス(困難を乗り越える力)」の象徴になる。
- 選手たちにも「トレーニング環境」「競技する機会」が提供される奨学金制度などのサポートがついていて、ただ名前だけではなく、実質的な支援がある。
しかし、難民選手団として競技に出ること自体が心身にプレッシャーになるケースもある。

アイデンティティとか居場所感とか、支援体制の継続性など、外からは見えにくい苦労もあるだろうね。
また、支援が一時的になってしまうこと、あるいは帰還の見通しが立たない人たちの心のケアなど、競技だけでなく、人生全体が関わる問題です。
そんな難民選手団ですが、実際はメディアの露出やファン・視聴者の認知度が十分でないこともあり、私のように「難民選手団って何?」と思う人が多いのかもしれません。
難民選手団ってどんな選手がいるの?
難民選手団には、印象的な選手とストーリーがあって、どれも「困難をどう乗り越えているか」が胸に来るものが多いです。
以下、いくつかピックアップしてまとめました。
- 出身はエチオピア。迫害を逃れて2017年にフランスに亡命。難民申請を経て暮らしている。
- パリオリンピックでは1500mで出場。東京世界陸上では5000mにも挑戦。
- フランスのストラスブールをベースにしていて、日常はトレーニングと仕事(倉庫で荷物梱包など)を両立している。
- 難民として過酷な道のりがあり、食生活や健康上の問題も乗り越えてきた。到着後、支援団体や地方自治体(町役場)などが「シューズや練習着をそろえる手助け」をしてくれたことが、彼女が競技を再び始められたきっかけになっている。
幼い頃に内戦で家族と離れ離れになり、ケニアのカクマ難民キャンプで育ちました。
キャンプの中で走ることを覚え、やがて国際的なコーチの目に留まり、トレーニングも受けられるようになりました。
2016年リオ五輪で難民選手団の旗手を務め、「難民の子どもたちに希望を届けたい」とスピーチした姿は世界中で大きな反響を呼びました。
スーダンの紛争から逃れ、難民キャンプで育ちました。
トラックもない環境で、砂地を走り込みながらトレーニングを積み重ね、国際大会への切符をつかみました。
彼はインタビューで「走ることは僕にとって自由の証。ゴールに向かって走るたびに、未来へ一歩近づいている気がする」と語っています。
まとめ
難民選手団は、単なるスポーツチームではありません。
彼らの姿は、私たちに「国を追われても夢を諦めない人がいる」という事実を伝え、世界の難民に目を向けるきっかけを与えてくれます。
世界陸上で難民選手団を見かけたら、それはただの競技者ではなく、過酷な運命を乗り越えて走り続ける人の物語だと思って応援してみてください。
きっとスポーツの見方が少し変わるはずです。

私のチャイルドが大きくなって陸上選手として活躍してくれたら嬉しいなぁ…なんて想像しちゃう。世界の子どもたちが将来の夢を諦めなくていいように、チャイルド・スポンサーとして少しでも応援できたらいいな。